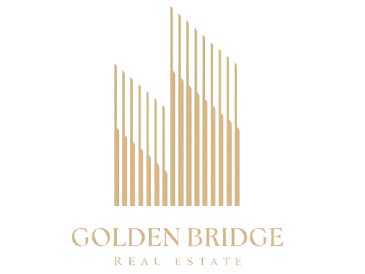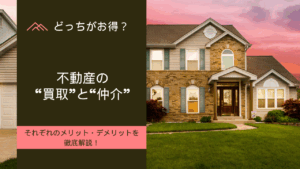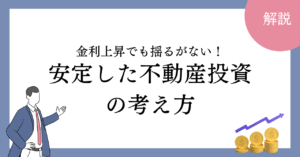日本では、少子高齢化や人口が減っていることが原因で、使われなくなった家(空き家)がどんどん増えていて、大きな社会問題になっています。国土交通省の推計によれば、2025年には空き家数が約950万戸に達し、空き家率は14.2%に上昇すると見込まれています。特に地方では、人が住んでいない家が増えることで、街の見た目がさびしくなったり、防災や安全の面でも問題が出てきています。
そんな中で最近注目されているのが、「住み継ぎ」という考え方です。これは、使われなくなった家を次に住む人へと引き継いでいき、もう一度活かしていこうという取り組みです。今回は、この空き家の現状と、「住み継ぎ」がどんなふうに役立つのかをご紹介していきます。
空き家問題のリアル
増え続ける「使われない住宅」
今、日本では家のうち約13.8%が空き家になっています。これは、だいたい7軒か8軒に1軒の割合で、誰も住んでいない家があるということです。特に、和歌山県や徳島県などの地方では、その割合がもっと高くなっていて、5軒に1軒以上が空き家になっている地域もあります。
主な原因
- 人口減少・高齢化:一人暮らしの高齢者が増えていることや、若い人たちが都会に出て行ってしまうことが、空き家が増える原因になっています。
- 新築偏重の住宅市場:日本では「新しい家に住みたい」という考えが強く、中古の家が売り買いされることは全体の15%にも満たないのが現状です。そのため、中古住宅はあまり選ばれず、使われないまま放置されてしまうケースが多くなっています。
- 相続問題:家を受け継ぐ人がはっきりしなかったり、相続されたあとにきちんと管理されなかったりすることがよくあります。その結果、誰の持ち物かわからないまま、どんどん古くなって傷んでいく家もあるのです。

「住み継ぎ」とは何か?
「住み継ぎ」とは、空き家を次に住む人へと引き渡していくという考え方です。単に家を売ったり貸したりするだけではなく、その家や地域にある思い出や歴史も一緒に受け継いでいくところが特徴です。
実際の事例
- 昔ながらの古い家をリフォームして、地域のカフェやみんなで住むシェアハウスとして活用
- 地方に引っ越したい人に対して、空き家をタダであげたり、とても安い値段で販売
- NPOや市役所などが、空き家を使いたい人と持ち主を結びつけるお手伝いを実施
このような取り組みは、空き家をよみがえらせるだけでなく、地域に新しい人がやってきたり、お店や仕事などの経済的な動きが生まれたりしています。

住み継ぎのメリットと課題
メリット
- 地域活性化:若い人や引っ越してきた人がその地域に住み続けることで、町に賑やかさや元気が戻ってきます。
- 歴史や文化の継承:昔ながらの古い家や伝統的な建物がそのままの形で大切に残される。
- 環境負荷の軽減:家を壊さずにそのまま使うことで、材料やエネルギーといった資源を有効活用。
課題
- リノベーションコスト:直したりリフォームしたりするのに、何百万円もの大きなお金がかかることもあります。
- 法的手続きの煩雑さ:誰の持ち物かわからなかったり、相続の手続きが終わっていなかったり、建物の使い道に制限があったりといった問題があります。
- 地域住民との関係構築:引っ越してくる人と、もともとその地域に住んでいる人たちとの間をつなぐサポート役が必要です。

今後に向けて
空き家を「未来の資産」に変える
空き家を「いらないもの」としてそのまま放っておくのではなく、新しく住んでくれる人につなげて、まちづくりに役立てるという考え方が、これからの日本にとってとても大事になります。そのためには、次のようなサポートが必要です。
- 誰のものかわからない土地を使えるようにしたり、相続の手続きをちゃんとやることをルールとして決めたりするなど、法律や仕組みを整えることです。
- 国や市町村が、お金のサポートをしたり、空き家を使いたい人と持ち主をうまくつなぐ仕組みをつくる。
- 民間の会社や地域のグループが協力し合って、空き家活用をいろいろな面からまとめてサポートする。

まとめ
空き家の問題は、ただの家の問題じゃなくて、その地域が元気をなくしているサインでもあります。でも、同時に地域をもっとよくするチャンスでもあるんです。
「住み継ぎ」というのは、古い家に新しい役割をあげて、その場所に新しい話をつくっていくことです。みんなが空き家をどう活かすか考えて動けば、日本の未来はもっと良くなっていくはずです。